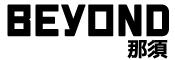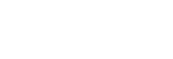インタープリテーション – 次世代観光の新潮流
次世代の観光体験を革新するインタープリテーションは、文化背景と教育アプローチの相違を超えて、旅行者に新たな学びと気付きの扉を開いています。海外と日本のインタープリテーションの違いは、19世紀の自然保護運動に遡る欧米の体系的な情報伝達アプローチと、日本の参加者の内発的気付きを促す「体験のデザイン」に鮮明に表れています。この多様な手法が、旅行者に豊かで深い学びの機会を提供しているのです。
日本と海外のインタープリテーション4つの違い
1.歴史的背景
海外の特徴
国立公園制度の発展とともに体系化(米国1916年)
アメリカでは、1916年に設立された国立公園局(NPS: National Park Service)が、インタープリテーションの発展に大きく貢献しました。初期のインタープリテーションは、公園の自然や文化的価値を来訪者に伝えるための解説活動として始まり、その後、フリーマン・ティルデン(1957年)の『Interpreting Our Heritage』の出版を機に、教育的・体験的な要素を取り入れた体系的なプログラムとして確立されていきます。現在では、NPSだけでなく、多くの国際的な保護地域管理機関がこの手法を採用しています。
日本の特徴
環境教育や地域振興と結びついて発展
日本では、1970年代以降の環境教育の広がりとともに、インタープリテーションが普及し始めました。1980年代には、エコツーリズムや地域資源を活用した環境学習の一環として取り入れられ、地域住民や旅行者を対象にしたプログラムが発展。2000年代以降は、環境教育促進法(2003年)やエコツーリズム推進法(2007年)の影響を受け、地域振興の手段としてのインタープリテーションが注目されるようになっていきました。特に、自然公園やユネスコエコパークなどでの活用が進んでいます。
2.情報伝達手法
海外の特徴
TORE理論(テーマ性・組織性・関連性・楽しさ)を重視したストーリーテリング
海外のインタープリテーションでは、TOREモデル(Thematic, Organized, Relevant, Enjoyable)がよく使われ、情報を体系的に伝えながら、参加者にとって関連性のあるストーリーを構築することが重要視されています。特にアメリカのNPS(国立公園局)や英国の解説手法では、単なる知識の伝達ではなく、訪問者が「なぜそれが重要なのか」を理解できるようなストーリーテリングが用いられています。
日本の特徴
五感を使った参加型ワークショップ
日本では、伝統的に自然との一体感や身体を使った体験を重視する傾向がある。五感を活用したプログラムも多いですが、それに限らず、フィールドワークや対話を通じた気づきを促す手法が主流です。例えば、森林インストラクターや環境教育プログラムでは、参加者自身が自然の中で「感じる」ことを大切にし、講師はその気づきを引き出すファシリテーションを行うことが多くあります。
海外は「ストーリー性を持たせた体系的な伝達」、日本は「体験を通じた気づきを促すスタイル」という違いがあるようです。
3.インタープリターの役割
海外の特徴
専門知識を持ち、ストーリーテリングを通じて伝える解説者
海外、特にアメリカやヨーロッパでは、インタープリターは単なる知識提供者ではなく、「意味づけ」を行う専門家とされています。フリーマン・ティルデンの提唱するインタープリテーションでは、単なる情報伝達ではなく、訪問者の感情や価値観に訴えかけることが重要とされ、ストーリーテリングの技術を活かしたプログラムも展開されています。国立公園や博物館のインタープリターは、エキスパートとして科学的・歴史的知識を持ちつつ、訪問者が興味を持ちやすい形で伝えるスキルが求めらています。
日本の特徴
体験や対話を通じて気付きを促すファシリテーター
日本では、インタープリターは単なる知識の伝達者ではなく、「場をつくる」存在とされることが多く、体験型プログラムや自然観察会では、参加者が自ら気づきを得ることが重視され、インタープリターはその気づきを引き出す役割を担っています。特に環境教育やエコツーリズムの分野では、一方的な説明ではなく、参加者との対話やワークショップを通じて学びを深めるスタイルが一般的です。
4.持続可能性との繋がり
海外の特徴
地域の持続可能性や課題解決を意識したプログラム設計
海外、特にアメリカやヨーロッパでは、国立公園や保護地域の管理方針とインタープリテーションが密接に結びついています。例えば、アメリカの国立公園局(NPS)では、訪問者に自然環境の価値を理解させることで、保全行動を促すことがインタープリテーションの重要な目的とされており、また、ヨーロッパでは、持続可能な観光の一環として、訪問者の環境負荷を抑えつつ、地域の文化や生態系を守るための教育的プログラムが組み込まれています。
日本の特徴
体験や対話を通じて気付きを促すファシリテーター
日本では、環境保護だけでなく、地域の課題解決や活性化と結びついたインタープリテーションが発展しています。例えば、過疎地域の活性化を目的としたエコツーリズムや伝統文化の継承プログラムでは、自然や文化の価値を伝えるだけでなく、地域経済の持続性も考慮され、また、国立公園や世界遺産エリアにおいても、観光と環境保全のバランスを取りながら、地域住民の関与を促すプログラムが増えてきています。


未来の旅行体験を変えるインタープリテーション全体計画を活用した観光プログラムの新潮流
旅行者の体験価値を高めるために、世界各地で進化を続けるインタープリテーションの手法。物語性の構築、参加型デザイン、地域資源の再解釈、そして危機対応教育といった視点を取り入れることで、単なる観光を超えた深い学びと感動を提供することが可能になるのではないでしょうか。
1. 物語性の構築
歴史と文化をつなぐストーリー
東南アジアのエコツーリズムでは、現地住民の生活史を物語形式で伝える手法が発展しており、訪問者が地域文化を感情的に受け止められるよう工夫されています。日本の観光地においても、古道や温泉地の歴史を、単なるデータの羅列ではなく、旅人が歩んできた道のりと結びつけるストーリーテリングの手法が求められます。例えば、温泉街では歴史上の人物がどのように癒やされてきたかを物語にすることで、旅行者の没入感を高めることができます。
東南アジアのエコツーリズム:「生活史の物語形式」事例
カンボジアのTmat Boeyのコミュニティエコツーリズム
狩猟禁止や自然保護の取り組みを「村の物語」として観光客に伝え、収益を地域開発基金に還元する循環システムを構築しています。また野生生物の保護活動を「村人の生活史」と結びつけたガイドツアーを実施などストーリーを伝えることで来訪者とのつながりを作り出しています。
Tmat Boey: Award-winning community-based ecotourism in Cambodia’s Northern Plains
マレーシア・サバ州のエコツーリズム
キウル地域の若者たちは、「ハイキングやトレッキングのツアー会社を設立した物語」を伝え環境保護意識を啓蒙し、さらにケンシウ族の伝統文化と豊かな自然環境について、歴史と自然が調和した公園として整備する計画という物語をケンシウ族の若者と共に生み出し観光資源化することで、持続可能な地域振興を目指しています。
The Benefits of Ecotourism: Stories from Local Communities
Storytelling for Sustainability in Developing Economy Tourism
研究論文では「ストーリーテリングが地域のエンパワーメントと文化保全に有効」ともいわれており、例えば、カンボジアのアヌルンプリングにおけるコミュニティでは「環境保護の個人体験談」を観光プログラムに組み込むなどの工夫も取り入れられています。


2. 参加型デザイン
体験を通じて深く学ぶ
北欧の森林ガイドツアーでは、「自分で道標を見つける」ナビゲーションゲームを取り入れ、訪問者が自ら考えながら進むことで理解を深める工夫がされています。日本でも、登山道や歴史的建造物を訪れる際、訪問者がアクティブに関われる要素を取り入れることが重要です。たとえば、山岳信仰の地で「巡礼者の視点」を体験するワークショップを開催したり、武家屋敷で当時の暮らしを再現する体験型プログラムを導入することで、より魅力的な観光コンテンツとなります。
北欧の森林ガイドツアー:「ゲーミフィケーション」事例
スウェーデン・ヨックモックの自主的探索アドベンチャー
雪原でのスノーシュー探検では「動物の足跡を追うゲーム」を導入し、参加者たちは自ら地図を読み解きながらシロフクロウの生息地を自主探索します。参加者が主体となりゲーム性を加えさらに生態系についての理解が深まる工夫が盛り込まれています。このようなゲーミフィケーションはEU森林研究所の報告書が「自主的探索が生態系理解を促進する」と分析している学術的根拠に基づいて開発されています。またスウェーデン環境保護庁では「自主的探索が地域文化への理解を深める」と報告されています。
Swedish Environmental Protection Agency


3. 地域資源の再解釈
新たな視点や解釈を与える
地中海沿岸のワイナリーでは、土壌分析データをワインの味覚体験と連動させることで、訪問者が科学的知識と感覚を同時に楽しめる工夫がされています。また、オーストラリアのアボリジニツアーでは、星図と神話を結びつけるナイトウォークが提供され、宇宙の広がりを文化的な文脈で体感できるプログラムが人気です。日本では、農業体験や地域の特産品に関する解説を、より学術的かつより体験的なものにすることで新たな視点による地域の再解釈が生まれるのではないでしょうか。例えば、地域の野菜栽培の歴史と土壌の関係を学ぶツアーや、山岳地域の生活と古来の伝承を組み合わせたプログラムは、訪問者の記憶に残りより深いローカル体験となるでしょう。
オーストラリア・キャプテンクック天文台:「地域再解釈」事例
オーストラリアの高速道路は星の運命に従っている
キャプテンクック天文台で行われている「ソングラインツアー」は、物語、歌、ダンス、芸術の伝統的儀式を通じて、地域の文化と天文学を結びつけるユニークな体験を提供しています。このツアーは、地域の文化を新しい視点から再発見する機会を提供し、訪問者に地元の歴史と伝統を深く理解させることを目指しており、また、このような体験は、地域の文化遺産を保護し、次世代に伝えるための重要な手段ともなっています。


4. 防災・危機対応教育
観光を通じて学ぶリスクマネジメント
イタリアのポンペイ遺跡では、火山防災教育を遺跡解説に統合し、観光と防災意識の向上を両立させています。また、カリブ海のサンゴ礁ツアーでは、気候変動の影響をダイバー自身が記録する市民科学プログラムが導入され、旅行者が環境保護の担い手となる仕組みが作られています。自然災害の多い地域では、単なる観光ではなく防災教育を組み込んだ体験コンテンツを造成することもこれからの持続可能な観光の実現に向けた新しいアイデアの一つです。例えば、活火山周辺でのトレッキングツアーでは、噴火の歴史や避難経路を学ぶ機会を提供することで、旅行者がリスクを意識しながら安全に楽しめる環境を作ることができます。
イタリア・ポンペイ:「観光と防災を効果的に融合」事例
防災視点で巡る遺跡ツアー
ヴェスヴィオ火山の噴火によって埋もれたポンペイ遺跡では、通常の観光ツアーに加え、「当時の災害が現代にどう役立つか」をテーマにした特別な教育ツアーが注目を集めています。このユニークなツアーでは、遺跡を巡りながら火山噴火時の住民の逃げ遅れの原因を分析し、現代の避難計画と比較することで、貴重な学びの機会を提供しています。過去の災害から得られる教訓を現代の防災対策に活かすという革新的なアプローチは、観光地としての価値を高めるだけでなく、地域社会への重要な貢献も果たしています。地域の防災センターや博物館との緊密な連携により、観光収益を防災教育プログラムの充実に還元し、観光と教育を効果的に融合させることで、持続可能なツーリズムの新しいモデルを確立しています。このような取り組みは、歴史遺産の保護と活用に新たな視点をもたらし、来訪者に深い学びの機会を提供すると同時に、地域の防災意識の向上にも大きく貢献しています。


今後の旅行体験においては、物語性のあるストーリーを構築し、参加者が主体的に学べるデザインを取り入れることが不可欠です。また、地域資源を新たな視点で捉え直し、観光を通じた危機対応教育の機会を提供することも重要となるでしょう。さらに、最新の技術を駆使しながら、多言語対応と持続可能な仕組みを構築することで、これからのインタープリテーションはより価値のあるものへと進化していくはずです。
これらの要素を取り入れる際に必要となるのが地域のインタープリテーション全体計画です。新しい旅行体験のデザインが、地域の観光業の未来を拓く鍵となるでしょう。
筆者:栃木アウトドア事業振興会BERGTOAD
筆者情報:インタープリテーション全体計画策定、コンテンツ造成、ガイド人材育成(国際資格)をトータルで1本化した支援を行っています。